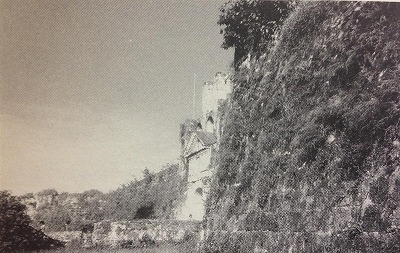こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
本日は、ひさびさに卵の都市伝説をご紹介。
数年前にネットで話題になった、謎の「たまごドリンクレシピ」があります。
それは、「ふき」と「たまごの白身」を組み合わせたレシピで、なんと一生に一度飲むだけで絶対に脳卒中で倒れなくなるというスンゴイ効果のドリンクなんですね。
実はこれ、
20年以上前、
ヘタすると30年前から面々と受け継がれている、
チェーンメール的都市伝説レシピなんですねー。
なにせ、
誰が書いたのか、
どこで始まったのか
これがサッパリわからない。
効き目も根拠もすごくアヤシイ。
なのに、ご年配の方々中心で全国に広まっている「謎レシピ」なんです。
レシピはたいていチラシのような形で出回っており、
文頭にはこんな文句が付いています。
『これは福岡市の小学校校長会で紹介された、参考文書の内容を要約したものです。国分市の養護老人ホーム”〇△園”で実施していて、国分市や隼人方面で大変な評判になっています。
今までに数千人の人が試され、そのことごとくの人々が健在であるという実験済みだそうです。
この飲み物は、一生に一度飲むだけでよいということですので興味をお持ちのかたは、早急にお試しください。また、お知り合いやお友達にもおひろめください。』
……との事です。
〇△の部分は、その時々で変わることもあるようですが、
国分市の部分はおおむね共通していたり、ホントナゾ多き紹介文。
そして、紹介されているレシピは以下のとおり↓
脳卒中で絶対に倒れない飲み物の作り方(一人分)
1、鶏卵・・・・・・・・・・・・一個(白味だけ)
2、ふきの葉の汁・・・・小さじ3杯
(ふきの葉の生を3?4枚切り刻むんで搾り潰し、それをこした汁)
3、清酒・・・・・・・・・・・・小さじ3杯 (焼酎は駄目)
4、梅漬・・・・・・・・・・1個をすりつぶす
(土用干しした梅干は駄目) 塩漬けにしてやわらかくなったもの
*注意:製法は必ず番号順に入れること。できるだけ一品を入れるごとによくかき混ぜること。
国分市の養護老人ホーム慶昌園で体験しているということで、国分市および隼人方面で大変評判。
* 梅の塩漬けの頃、入梅の6月頃には、ふきも梅も手に入ります。
(福岡市の校長会で配布の資料)
—————————
脳卒中で絶対に倒れない飲み物の作り方(一人分)
(1)鶏卵 : 一個(白身だけを使う)
(2)ふきの葉の汁 : 小さじ3杯 (ふきの葉を3枚ほど切り刻んですりつぶして濾した汁)
(3)清酒 : 小さじ3杯 (焼酎は駄目)
(4)梅漬 : 1個を細かくつぶす (土用干ししていないもの)
*注意:製法は必ず番号順に入れること。できるだけ一品を入れるごとによくかき混ぜること。
—————————
ナルホド、お酒ドリンクなんですねー。
他のチェーンメールと同じく複数のバージョンが存在するのですが、レシピについてはおおむねどれもおんなじ。
ふきの葉は食物繊維を豊富に含みますが、
栄養的には他の野菜とくらべそれほど多くありません。
卵の黄身には確かに、
血管を強くして脳卒中のリスクを下げる栄養素がたくさんあります。
が、『毎日きちんと食べた場合』の効能であって、
「一生に一度食べて効く」ほどの劇的な効果は、
残念ながら無いんですねー。(ーー;)
厚生労働省の統計データによると、
脳卒中の死亡は年間約13万人、人口の約0.1%です。
一年間で区切ると「1000人中999人は脳卒中では死なない」…とも言えます。
そういう意味ではこの謎ドリンク、
飲んでも飲まなくてもほとんどの方は、書いてある通りの効能になるっちゃァなるわけですが・・・・・・(^^;)
◆「暦」から来たコラボ伝説か!?
なんでこんなレシピが生まれたのか、を私なりに考察しますと、これは「大寒」のこよみが元になっているんじゃないかと思います。
実は「ふき」と「たまご」は、まさに今の時期『大寒』(1月下旬-2月初旬)を指すキーワードなんですね。
二十四節気のひとつ「大寒」の時期は、七十二候で表現すると「款冬華」と書いて「ふきのはなさく」と読みます。
また同じ時期を中国では「鶏始乳(にわとりはじめてにゅうす)」とも書き表わします。(※注1)
前者は「ふきが目を出す頃」という意味で、
後者は「春が近づき鶏が卵を産み始める頃」という意味です。
それとは別に、ニワトリさんが初めて産む頃の卵・「初産み卵」は『中風(脳卒中の後遺症)を予防する』とのいわれが古来よりあります。
よって、
時期が同じ「卵=ふき」のイメージ + 「初産み卵の効能」
→ 「脳卒中に効く、卵とふきの特別ドリンク」
というところに繋がったんじゃないでしょうか?
(※注1:日本では「款冬華」直後の時期を「鶏始乳」と呼びます)
「いわしの頭も信心から」とも言います。
上のレシピ、少なくともカラダに悪いわけじゃありませんので、ダメ元でお試しいただくのも・・・・まァ面白いかもしれません。(^^;)
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。
(関連:【たまごの都市伝説】秋分の日に立つ卵- たまごのソムリエ日記)
(関連:【たまごの都市伝説】1卵+2携帯電話=??(携帯への恐怖!) – たまごのソムリエ日記)