 こんにちは!こばやしです。
こんにちは!こばやしです。
少し前、妻と映画「ガリバー」を観に行ってきました。
さて、このガリバー旅行記の有名エピソード「ガリバー小人国へ行く」ですが、実は「ゆでたまご」が物語の重要キーワードになっているのをご存知でしょうか?
「子供のころに読んだけど、どんな話だっけなぁ・・?」という方も多いかと思います、
簡単に粗筋を紹介すると、
—————————————————–
船医であるガリバーは航海中、嵐に遭い難破、小人たちの国「リリパ ット王国」に打ち上げられる。 彼らは非常に驚きつつも、“巨人”であるガリバーを客人としてもてなす。
ット王国」に打ち上げられる。 彼らは非常に驚きつつも、“巨人”であるガリバーを客人としてもてなす。
一方王国の 隣には「ブレフスキュ国」があり、お互いに仲が悪く戦争状態にあった。 リリパット王(皇帝)の求めに応じガリバーは戦争に協力、ブレフスキュ国連合艦隊を見事打ち破る。 しかし、国内の陰謀に巻き込まれ暗殺されそうになり隣国ブレフスキュ国へ亡命、その後ボートで出航、商船に拾われて故郷へ帰る。
—————————————————–
と、まぁこんな内容です。 絵本でガリバーが沢山の船を綱で引っ張ってるのは、このブレフスキュ国連合艦隊“拿捕”のシーンですね。
さて、問題はこの「リリパット王国」と、「ブレフスキュ国」。
この二国間で戦争の原因が、なんと!「ゆでたまごの剥き方」だったんです。
◆あなたはどっち派? ゆでたまごの剥き方
ガリバーが流れ着いたリリパット王国は「小さいほうの円弧から割る」派で、お隣ブレフスキュ国は「大きい方の円弧から割る」派。 リリパット王国では「大きい方から割る派」は官職にも就けず、「大きい円弧から割る食べ方」について書かれた本はすべて発禁。 といった有様・・・。

もともとリリパット王国も「大きい円弧から割る」のが正統だったのですが、リリパット先々代皇帝がこの方式で指を切ってしまったことから心変わりし、「これからは『小さい円弧から割る』ようにせよ。」と勅令を出します。
さあ、これに猛反発したのが国民。
「大きい円弧」原理主義者は6度の内乱を起こして抵抗、「小さい方から割るくらいなら死んでやる!」と処刑されたヒトの数なんと1万1000人・・・! 残った反対派はゲリラ化し潜伏、大半は「大きい方から割ること」を国是とする隣国ブレフスキュ王国へ亡命してしまいます。
この事が、長く続く二国間の戦争を招いてしまうわけです・・・。
うーむ。 どっちでもいいじゃん、バカバカしくもけっこうハードな内容なんですねぇ。ガリバー旅行記は。 しかし・・・
◆「ゆでたまご」は何を例えている?
この「ガリバー旅行記」、実は大人向けの鋭い風刺物語なんですね。 ここで言う「ゆでたまごの剥き方」論争は、当時の「カトリック」と「プロテスタント」の諍いを皮肉っているわけです。 リリパット王国とブレフスキュ国は、イングランドとフランスのパロディ。
つまり、「どっちも同じキリスト教でしょ? 教義のいさかいなんて、『ゆでたまごの剥き方』くらいどうでもイイことジャないの。 そう思いません?」と、揶揄してるんです。
我々にはピンとこなくても、当時の人たちにとってはすぐに分ることだったわけです。 例えるなら「ミンチュ党とジーミン党があって、互いに言い争いをしていました・・・」と書かれると、現代の大人なら、「ああ、なるほどね。」となるわけです。
さて、
「ガリバー旅行記」が書かれた英国。 現在、若者の8割が「ゆでたまご」の茹でかたを知らないという驚きの調査結果があります。 徹底的に「ゆでたまご」にこだわった寓話を描く「ガリバー旅行記」は、現代の英国世情まで風刺しているようにも見えますねェ (^^)
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。

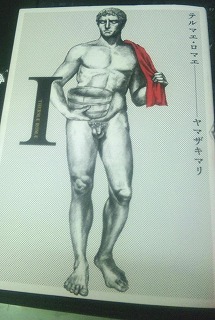 こんにちは!こばやしです。
こんにちは!こばやしです。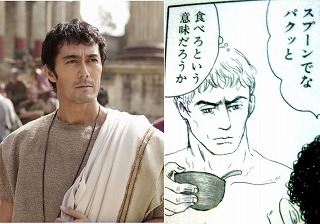
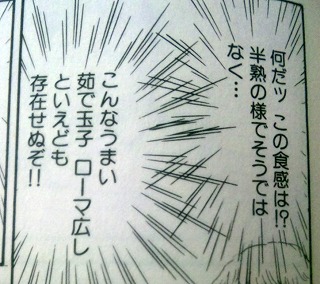


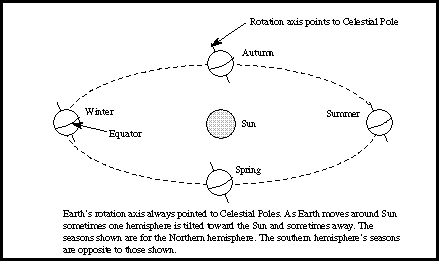
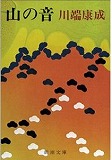


 信) – Yahoo!ニュース
信) – Yahoo!ニュース




 どれも、卵とウサギが一緒に描かれています。
この組み合わせは、欧米ではしょっちゅう目にするモチーフなんです。
これはキリスト教、
どれも、卵とウサギが一緒に描かれています。
この組み合わせは、欧米ではしょっちゅう目にするモチーフなんです。
これはキリスト教、
