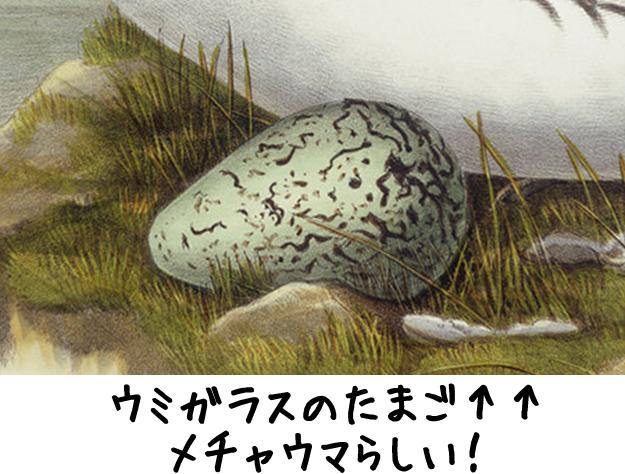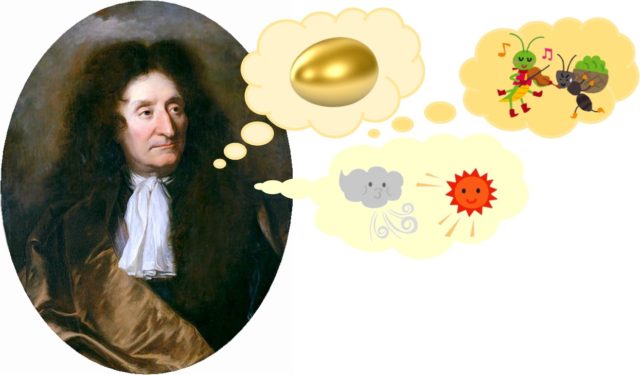 こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
本日4月13日は、17世紀フランスの詩人ジャン・ド・ラ・フォンテーヌさんの命日です。
日本では名前はそこまで知られていませんが、
イソップ物語を元にした沢山の寓話詩を創っていまして、世界中で有名な方です。
いわゆるイソップ童話って、紀元前6世紀・今から2500年以上も前のお話なんですね。
なので、現代ではわかりにくい部分や、流れが唐突だったり、また当時の言葉(古代ギリシャ語)での韻を大事にした内容もあり、現代ではちょっと難解なものも多いのです。
それを、上質で分かり易いストーリーとして仕上げなおし、またテンポ良く聴きやすい言葉やお話の流れにしたのが、ラフォンテーヌさん。
「北風と太陽」
「アリとコオロギ」
「オオカミと(7人の)子ヤギ」
などは聴いた事ありますよね?
日本人の僕たちが、これらイソップ童話に子供のころから親しめているのは、言うなればラフォンテーヌさんのおかげ。
そして特に、
僕にとってゆかりがあるのは、
「金の卵を産むめんどり」
の寓話詩を作った人だから。
〇黄金の価値になる卵!?
当社の名前は45年前から「小林ゴールドエッグ」、金のたまごです^^
ストーリーは、
「貧しい男が飼う一羽の鶏が、ある日から毎日一個、金の卵を産むようになった。
おかげで男はずいぶん金持ちになったが、それじゃ満足できない、もっと沢山金がほしいと考えた。
腹の中に金のカタマリがあるはずだ!と鶏の腹を裂いてみたら、なーんにも入ってない。
鶏は死んでしまったので、もう金の卵も手に入らない。再び貧しい生活に逆戻りしてしまった。」
というお話ですね。

ウチの社名を考えたのは亡くなったボクの父・先代です。
由来をちゃんと聞いたことは無かったですが、
堅実な性格でしたのでおそらくこの寓話のように
「たまごという食材は黄金の価値がある」
「無理して儲けに走ってはいけない」
・・・・・・こんな想いを込めていたんじゃないかと思います。
ステキな寓話と商売の戒めをくださった、ラフォンテーヌさんに感謝ですね~。
ここまでおよみくださって、ありがとうございます。

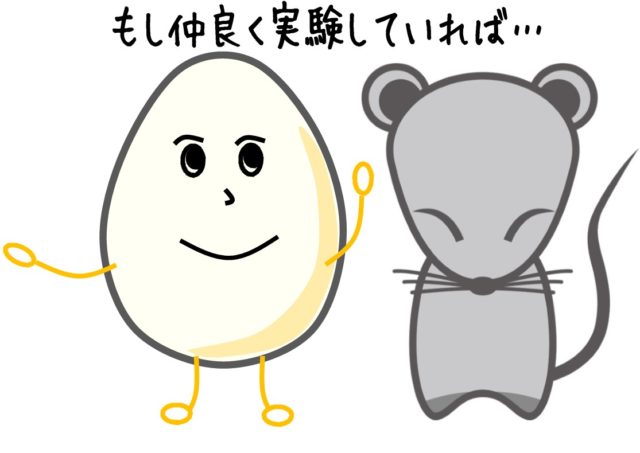
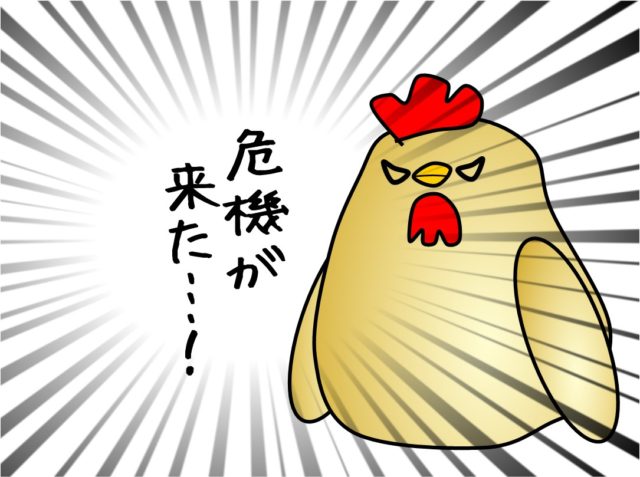 こんにちは!たまごのソムリエ・小林です。
こんにちは!たまごのソムリエ・小林です。