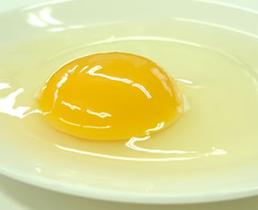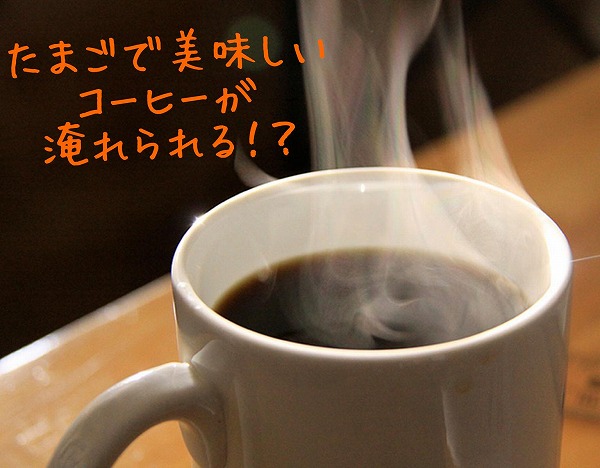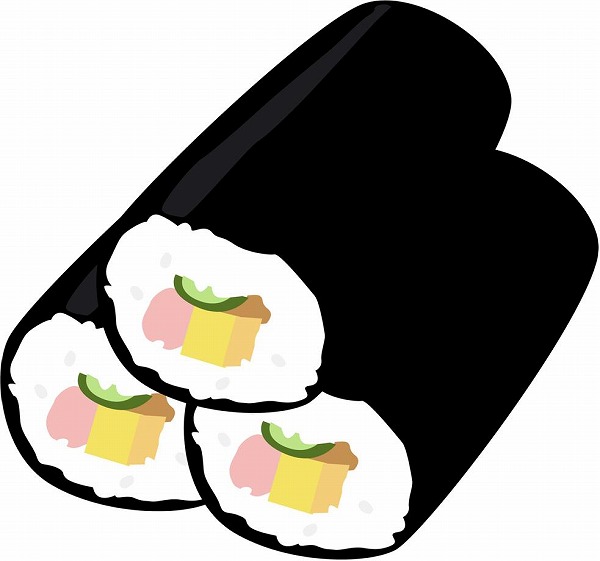こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
生ものである鶏卵は、ほぼ「国産」です。
たまごの国内消費は260万トン(平成21年)。
個数にして400億個が毎年食べられており、そのうちごく一部が加工用として輸入されています。
割合でいうと、『95%が国産』なんです。
・・・・・・が、「自給率」という側面で考えると、実はまったく違ってくるんですね。
日本の鶏卵自給率は、わずか10%です。
え・・・??? どういうこと??
な、なんでこんなに違うのかと言うと、それは飼料のせい。
ニワトリさんの飼料を、輸入に頼っているから。
ニワトリさんの飼料にはトウモロコシや大豆、小麦など穀物がたっぷり配合されており、国土の狭い日本としては、良質な穀物の供給をしようとすると米国やカナダなどからの輸入に頼らざるを得ないんですね。
そして、日本は「カロリーベース」という自給率換算方法を採っているため、たまごの場合、『たまご一個を作るのに必要な飼料カロリーのうち国産比率が何%なのか?』 が自給率に換算されてしまいます。
なので、卵は国内で産まれても、
そのための“飼料”輸入割合が高いですから、
最終的に自給率10%
となってしまうわけです。
このことは、いざ輸入が止まったときのことを考えると、ゆゆしき問題でもあります。
じっさい農水省のシュミレーションによると、もし世界的災害などで一切の輸入が停止したとなると、
まず食べられなくなるのが牛肉、次いで卵、
なのだとか。
ですので、
ニワトリさんにもっと国産の穀物をたべてもらう。
こういった取り組みがなされています。
休耕田を利用した飼料米の栽培に補助金を出すなど、いくつかの試みがなされています。
私達の商品でも、
『香川県産の玄米飼料を食べて育った鶏の卵』
『徳島県産すだちや鳴門金時さつまいも配合飼料を食べて育った卵』
などをお届けしておりまして、
より美味しいもの、
かつ、少しでも自給率に貢献できるたまごを沢山の方に食べて頂くお手伝いをしております^^
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。