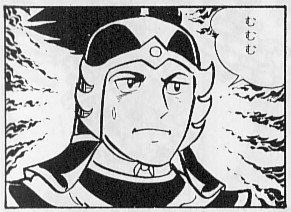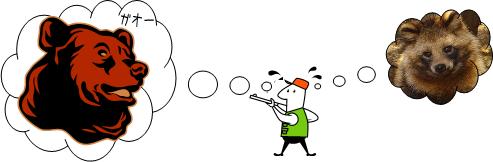こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
たまご鶏のことわざ18弾、今回は欧米から。
<卵を採ろうとする者は、鶏の鳴き声をガマンせよ>
(He that would have eggs must endure the cackling of hens)
『何か楽しみを得ようと思ったら、別のところでガマンが必要です。』という意味です。楽しいことばっかりじゃないんですよねー。
将来良い仕事に就きたいから猛勉強する、
出世するからこそ、気苦労も多い。
隣の芝は青く見えがちですが、どの仕事、立場でもそれなりのガマンがあるのではないでしょうか。
ところで、数万人の職場リーダー・経営者を取材・統計をまとめ著書にした経営思想家マーカス・バッキンガムさんによると、
「何をガマンできるかはその人の才能」なんだそうです。 例えば「看護師さんの才能」であれば、注射を打つスキルが高いかどうかじゃなくて、例えば夜勤やハードな仕事であっても患者さんの「ありがとう」の一言で疲れが吹っ飛ぶ、そんな性分かどうかの方がずっと大切で、これすなわち“才能”なんですね。
鶏の鳴き声をガマンしなくちゃいけないのは仕方ないとしても、それを「いやだなァー。」と強く感じる人と「結構カワイイ声じゃん。」と感じる人では、そのガマン度合が違うわけです。
自分にとってのガマンが平気な「鶏の鳴き声」を見つけることが、天職に出会うコツなのかもしれません。
ちなみに鶏さんは、そんなにうるさくないです。 普段は「コー・コー」と静かに鳴いてるくらいで、近くでいても騒がしいなんてあんまり思わないんですよねェ。
いちおう鶏サンの名誉のために弁解しときます(^^)
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。