初回限定!お試しセット
人気5種類ソムリエたまごお試しセット

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
先週末は、えびす祭りのお参りに行ってきました。
徳島では「えべっさん。」と呼ばれて、親しまれています。
えびす様はもともと海神で漁業の神さんなのですが、平安時代には「市場の神様」だったそうで、そこから転じて商売繁盛の神様として祀られています。 ただし、「えびす様が商売の神さん」、ってのはどうも関西中心みたいですねー。
徳島では徳島駅前から歩いて数分、通町(とおりまち)の事代主神社で毎年1月にお祭りがあります。 1月9日から11日の3日間、ウチは先代の頃よりずっと「のこりえびす」、最終日にお参りをしてるんですね。 毎年でっかい声で「商売繁盛!」のお祈りをしております。
今年は11日は土曜日、週末という事もあって例年以上ににぎやかで、狭い路地が出店と人でいっぱい。(^^)

売ってるものもチョイと高いですが、まァそこは縁起物ですから、かならず何かを買って帰ってスタッフのみんなと食べるんですね。
さて、以前にも書きましたが「えびす様」は早起きしたニワトリさんのせいでサメに足を噛まれたため、ニワトリさんが嫌いなんです。(参照→たまごのソムリエ日記)
そこんところは“海神だったころの名残”で今は「商売の神様」ですし、居並ぶ露店もお菓子やたこ焼き・揚げ物と「卵を使ったもん」オンパレードで大繁盛しています、「美味しいもん」を世の中に届けるために頑張る「たまご屋」を広い心で応援してくれるものと思い、毎年感謝とお祈りをささげております(^^)
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
正月三が日は息子と連日たこあげをしていました。(^^)
凧揚げ自体は紀元前からあったけれども娯楽としての“正月に凧揚げをする風習”は江戸時代になって普及した、と言われています。
たまごも紀元前から日本にあったものの、庶民の間で広く食べるようになったのは江戸時代から。
なんだか共通するものを感じますねー。
そういえば「たこ」という呼び名は実は関東限定で、むかしは関西地域では「いか」だったのだとか。ビックリです。
徳島は関西にほど近いのですが、「いか揚げ」だったのでしょうか!? 興味深いです。

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
本年初更新です!
昨年後半より、思い立ってほぼ毎日更新にしてみたのですが、今年もなるべくこの更新頻度で頑張れたらと思ってます。
今年は午年(うまどし)ですね!
ウマとたまご、共通点を挙げるとすると、それはどちらも「金運を運んでくる」といういわれがある点。
たとえば「左馬」なんて言葉がありまして、
馬は右側から乗ると転んで左側から乗ると転ばないと言われることから、「左馬はトラブルなく順調に行くことの表れ」として馬の字を反転させたものをお守りにしたりします。
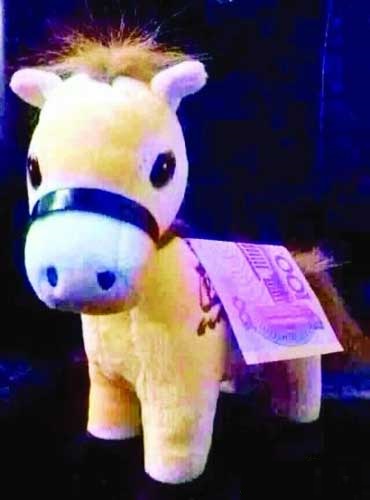
また、今年年末に中国で流行ったのは、馬の置物の上にお金や欲しいものの写真・ミニチュアを置くというもの。 これは、中国語で「馬上」と書いて「すぐに」という意味を表わすため、馬の鞍にものを置くと「すぐに手に入る」というジンクス話が広まったためです。 (参照:http://www.xinhuaxia.jp/1131334123)
そして、我らが「たまご」
これは、「金のたまご」と言われるように、西洋中心で蓄財の象徴として、金運の上がるジンクスとなる物とされています。 また、中国発祥として、『大寒ごろ生まれのたまごを食べると一年間金運が上がる』という言い伝えもあります。
ぜひ、馬の置物と玉子料理、両方あわせて一年の金運を大幅にアップさせてくださいませ!
本年もどうぞよろしくお願いします!(^^)

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
週末に家族で畑にあるミカンの木の収穫をしました。

そんなに本数は無いのですが、なにせ間引き?などは一切していませんので、一本の木にたーくさんなってるんですねー。

徳島の先週末はとにかく天気がよくてあったかく、最高の収穫日よりでした(^^)
無農薬なんで見た目は悪いですが、今年は夏の暑さが良かったのか結構甘くてなかなかの良いデキ。満足です。
私、卵が一番なのは別として、重度のミカン好きなんですね。一箱あっても一人で一週間もたないくらい食べ続けます。
しばらくたーくさんありますので、年末正月は楽しめそうです。
こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
ネーミングと語感について、ふと思ったことを。
ドラマ「リーガルハイ2」、いよいよクライマックスですね!
この人気ドラマの主人公、名前が「古美門(こみかど)」弁護士というのですが、このお名前けっこう珍しいですがそこまで奇異に感じる語感ではありませんね。
米国の人気ドラマシリーズ「HEROES」では、主役の一人・日本人「ヒロ」の勤める会社は「ヤマガト工業」と言います。
これは結構違和感がありますね。
「コミカド」と「ヤマガト」
海外の人からすると、どちらもニュアンスとして変わらない印象のようです。
しかし日本人的には前者はアリで、後者はナシ。
この名前の語感に対する感覚はいったいどこから来るのか・・・? これ興味深いですねー。
反対に、海外の人にとって
マリオの「ピーチ姫」 → あり得ない
紅の豚の「ポルコ・ロッソ」 → これまた可笑しい名前に感じるのだそうです。
これは日本人にとっては分からない・・・。
こういうのって「なぜ名前としてこの語感はナシなのか?」を理屈で説明するのって、相当難しい気がします。
小説や映画、創作物ではたくさんの「珍しい名前」が作られます。上記の「コミカド」もそうですし、人気ライトノベル作家西尾維新さんの作品には「戦場ヶ原(せんじょうがはら)」という苗字を持つ登場人物が出てきます。
もちろん現実にそんな苗字はないのですが、それでも「ヤマガト」に比べると違和感は薄いのが不思議です。
文化的なものからくるのだと思いますが、それぞれの国で、いったいどれくらい住めばこのヘンが理解できるんでしょうねー。 徳島県らしい名前、四国らしい名前、なんてニュアンスもあるのかもしれません。
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。(^^)

人気5種類ソムリエたまごお試しセット

製品、サービスに関するお問い合わせ