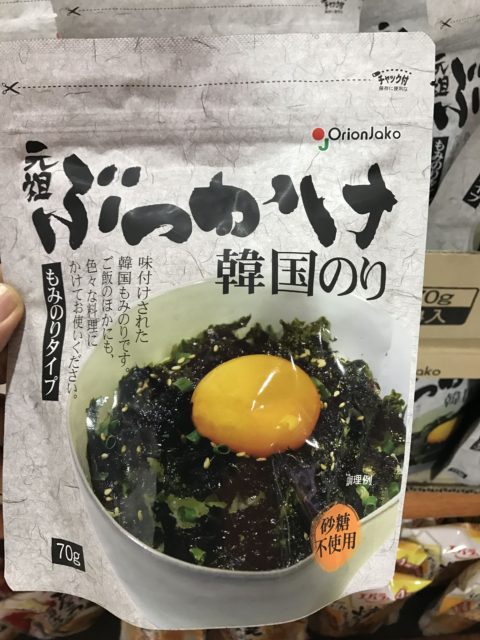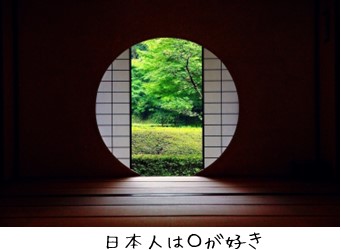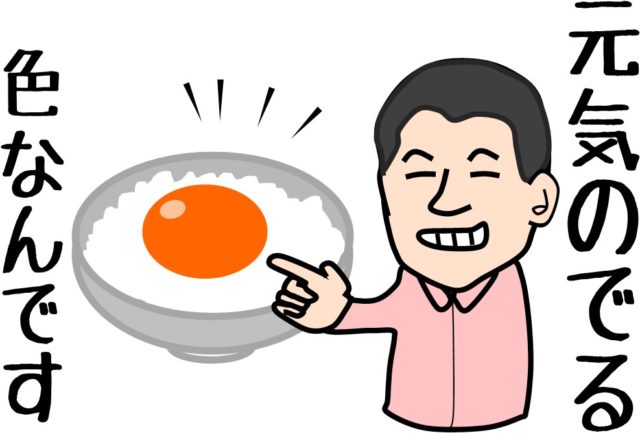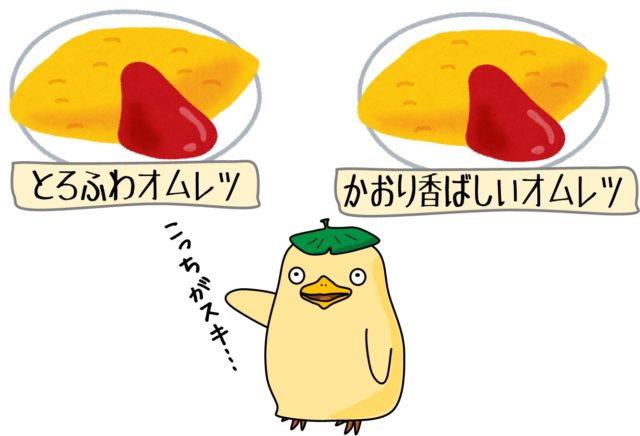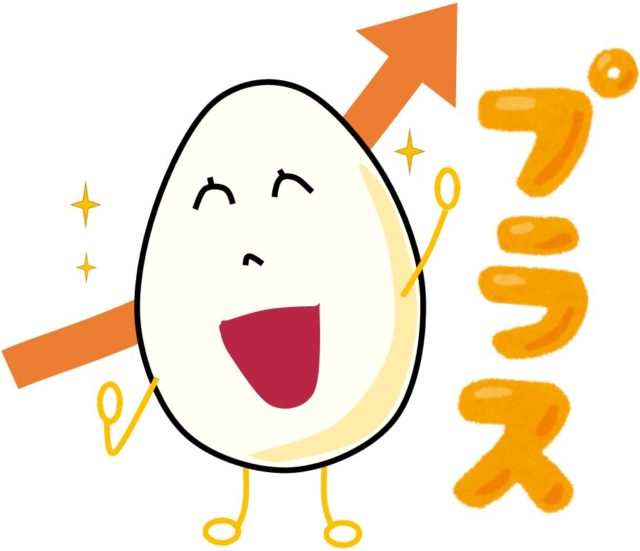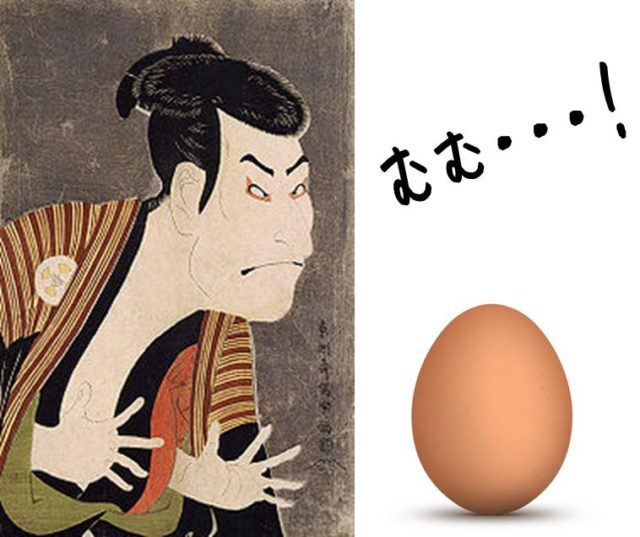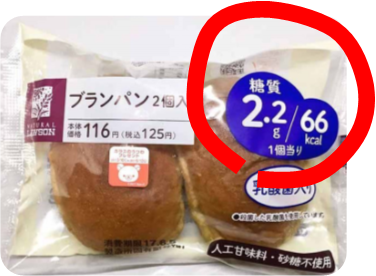
こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
写真はコンビニの商品ですが、
わりとでっかく「糖質」の数値が書いてあります。
この商品に限らず、最近はこんな風に「糖質」量を判りやすく書いてある食品やメニューが増えました。
これはもちろん「糖質制限」をする人が増えたから。
「ゆるい糖質制限」流行りがコロナで更に加速、
日清オイリオ調べのデータによると、なんと半数以上の人が「糖質制限ダイエットに挑戦したことがある」と答えています。
みんな食べ物の糖質量を知りたい、低糖質で食べたい!‥‥‥のです。
こうした風潮を受けて、カレーチェーン店coco壱番屋でも御飯の代わりにカリフラワーを使った低糖質カレーや、牛丼チェーンすき屋では御飯の代わりに豆腐を使った低糖質牛丼を展開、大きくページを取っているなど、大手外食店でも糖質制限ニーズに対応した動きを広げていますね。
コロナ禍の影響で、運動量が減ったこと、健康面での意識の高まりが要因じゃないかと思います。
〇低糖質ブームをメニューに取り入れるには?
健康面のメニュー強化や打ち出し方の改善は、ぜひ外食さんでも取り組むべきテーマになっていますね。
糖質制限の風潮を外食さんで取り入れるとすると、下記の2つがあります。
➀炭水化物などの糖質食材を、低糖質に置き換える
②糖質量をメニューに「表示」し、お客さんの方で一日摂取量をコントロールしてもらう
まず➀ですが、これは、
ごはん → ブロッコリーやカリフラワーを砕いたもの・豆腐・こんにゃく米
麺 → こんにゃく
などに置き換えるだけ、ですね。
メリットは、常備しておくとオペレーションは比較的そのままでもお客様にご提供ができる点です。「良かったら御飯をこちらに変更できますよ。」みたいな。
また、小麦粉よりも全粒粉の方が3割ほど糖質が少ないですから、メニューによって全粒粉に切り替えることも必要かもです。
そして②の「表示」ですが、これはざっくり計算してみると良いかと思います。
〇お店のメニュー糖質量を計算してみよう
まず、メニューに使われる食材の成分量を書きだします。
いろんな目安になるサイトもありますが、文部科学省の「食品成分データベース」がオススメです。
糖質量 = 炭水化物量 ― 食物繊維
として計算しますので、
上記データベースで「食材」を入力、炭水化物と食物繊維量(『他の成分を表示』で表示されます)を書きだして、引き算します。
数値は「100gあたり」なのでレシピに合わせて計算し、全部を足すと完成です。
特にメニュー内容やオペレーションをいじるわけじゃありません。
これだけ関心持った人が増えたわけですから、せめて糖質量「表記」はすぐに始めても良いんじゃないかと思います。

上記はサンドイッチの「サブウェイ」メニュー表記です。こんなカンジで小さく書いておけば問題無いかと思いますが、せっかくなのでヘルシーメニューを作ってPRするのも面白いですよね。
ちなみに卵は卵の糖質はほぼゼロ!なので低糖質メニューには最適です。
卵に唯一不足するビタミンCや食物繊維とあわせ、夏野菜でバランスメニューをぜひ試してみて下さいませ~!
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。