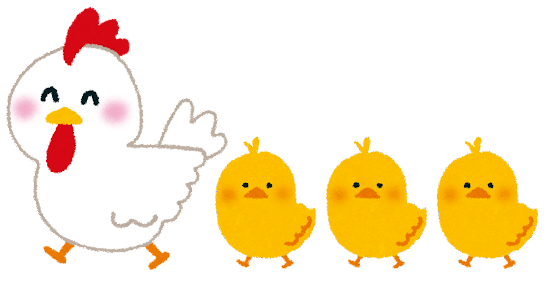こんにちは!
たまごのソムリエ・こばやしです。
万博でポルトガル館に行った際、
「そういえばポルトガルに
『たまごかけごはん』みたいな
スイーツがあったっけ。」
とふと思い出しました。
_
「アローシュ・ドース」
直訳すると「甘い米」。
お米でつくった
あま~いスイーツです。

お米プラス卵黄をつかいますので、
素材が「TKG」なんですね。

おかゆっぽいといいますか、
お米とろとろのプリンみたいなお菓子でして
英語名もそのまま「ライスプリン」です。

お米の食感もちゃんと残っていて
日本人的には不思議なカンジ・・・
_
食べ慣れたお米の口当たりと
舌に感じる意外な甘みに
「塩味じゃない!?」と
面白い違和感を感じるかも。
_
ポルトガル政府観光局が出している
アローシュ・ドース(アローズドーセ)
のレシピは下記のとおり。
(こばやしが日本流に少し変えてあります)
<材料>
お米 300g
水 600ml
砂糖 350g
成分無調整牛乳 2000g
卵の黄身 120g
バター 大さじ1
レモンの皮すりおろし 1個分
シナモンスティック 1本
塩 1つまみ
<作り方>
①水にバター、レモン、シナモン、塩を入れ沸騰させる。
②米を加え煮る
(水分が無くなるまで・10分くらい)
③水っぽさがなくなったら、
牛乳を少しずつ加えながら中火で加熱
へらでかき混ぜ続ける。
④最後の牛乳を加えて少し煮詰まったら、
砂糖を加える。
⑤砂糖が完全に溶けた後、
おおさじ3杯くらいを小皿にとりわけ、
そこに黄身を加えて混ぜる。
⑥それを鍋に入れかき混ぜて、
とろとろのカスタード状になる
82℃~85℃までじっくり加熱する。
⑦冷まして、シナモンパウダーを少しかけて出来上がり。
火加減さえ間違えなければ
さほど難しくはありません。

◆日本に伝わるびっくりなポルトガル料理
ポルトガル料理って、かつて
戦国時代に日本に伝わっているんですね。
_
天ぷら、カステラ、金平糖
なんかがそうです。
天ぷらはポルトガルのフリットから。
カステラなんてカスティーリャ地方の
呼び名がそのまま名前になっちゃってます。
ほかにも
ポルトガル語が由来となった言葉として
「カルタ」とか「コップ」「ボタン」
なんかがありますね。
_
我が徳島県にも
モラエスさんという方が
ポルトガルから明治時代に
永住してくださって、
その文化をポルトガルに
伝え続けてくれました。
(日本について書いた本が、欧州で当時ベストセラーに)
なので県民はポルトガルに対する
良い印象がほかの国よりも
大きいんですね~。
_
お米と卵のアローシュ・ドース、
あなたのお店のご繁盛メニューの
ヒントになりましたら幸いです。
ここまでお読みくださって
ありがとうございます。
(参照:ポルトガルの伝統的なレシピ: アローズドーセ(ライスプディング) | www.visitportugal.com)