
こんにちは!
たまごのソムリエ・こばやしです。
僕はレシピ本を読むのが好きです。
新刊のを読むのも好きですし、
古書店をめぐって古いレシピ本を
探すのも非常に面白いんです。
時代に合わせて新しい料理も
次々と出ていますが、
人間の舌には普遍的な好みだって
ちゃんとありまして、
昔ながらの料理でも
うならされるくらい美味しいものがたくさんあります。
たとえば、
「Je sais cuisiner(キッチンについてのすべて)」
というレシピ本があります。
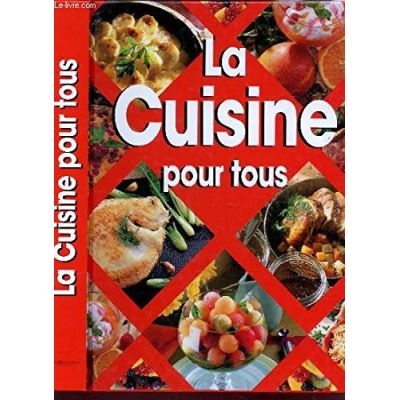
ジネット・マティオさんと
H・ドラジェさんという方が編集した
フランス料理本でして、
原著は1923年のものですが
あまりにヒットした名著で、
何度も何度も編纂しなおした
新しいバージョンが再販され続けています。
2000を超えるレシピがありまして
なんとオムレツだけでも
42ものレシピが載ってます。
すごいですね~。
おばあちゃんから娘、孫へと
何世代にもわたって、
伝えられるレシピ本です。
最近の本で面白かったのは
たまごサンド専門書でレシピ本
「卵とパンの組み立て方」(新光社)

パンのコト・たまごのコト
その相性・・・
玉子サンドについてだけで
200ページ近くもあるステキ本です。
あとオムライスだけのレシピ本
「バズる!オムライスレシピ」(角川書店)
が尖っていて面白かったですね~。

この本の紹介するオムライス
レシピ数はなんと43種。

冒頭のフランスの古典的名著の
オムレツレシピ42種類と
ちょうど1種ちがいですから、
もしかすると意識して数を合わせた!?
のかもしれませんね。
愛知の有名オムライス店の2代目さんが
書かれているのですが
1種でも時代とともに名著を超えてやる!
みたいな気概があっての
オマージュ精神が宿っている
のかもしれないな~と感じます。
◆プロこそ市販レシピ本を読むべき
レシピ本の多くは、
対象を「家庭で料理を作る人」
に据えています。
プロの料理人さんならば
「いまさら読んでもしょうがない。」
みたいに感じられるかもしれません。
ですが、
一般のご家庭料理として
魅力的に映るレシピ
そこに「プロ目線のアレンジ力」
を乗せることができれば、
あなたのお店のヒットメニューとして
非常に大きなヒントになるのではないでしょうか。
アレンジできる視点で
簡略化されたレシピを
また見直すと、
とんでもない気づきになるかもしれません。
ちょうど、百年前のレシピを
何度も何度も編纂しなおすように…!
ここまでお読みくださって、
ありがとうございます。

























