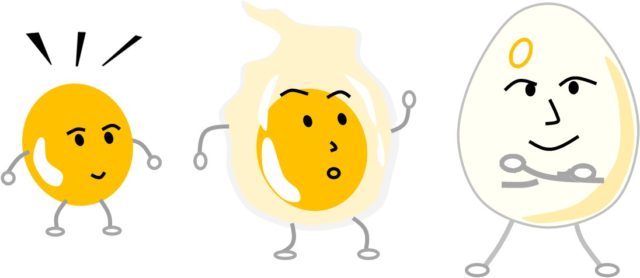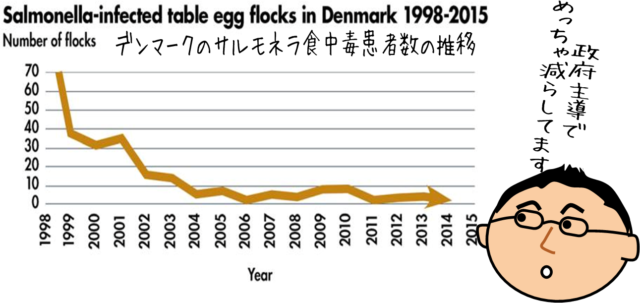本日はご飲食様向けの、メニューのお話を。
こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
今週は中秋の名月でした。
日本では月見うどんなんてものがありますが
中国でも「黄身=月」の
見たて料理があります。

蛋黄月餅(たんふぁんげっぺい)って言いまして、
中秋節・十五夜の月見に食べるお菓子「月餅」に、
更に塩漬けのアヒルのゆで卵黄身を入れたもの。
あんこの中に鮮やかな黄色の黄身があって、
なるほど名月、ってカンジがします。
塩味とあんこがまた合うんです!
僕もかなり好きな味なんですよね~。
横浜中華街のホテルでは、
なんと直径1メートル
重さ約60キロで
皮の生地だけで12キロ
アヒルの塩卵700個もつかった
大蛋黄月餅が展示されていました。

すごいですね~。
ちなみに中秋節を過ぎると
月餅は大量に投げ売りされるそうで、
なんだかクリスマスケーキみたいですね。
ちなみに台湾にも『蛋黄酥』なる同様のお菓子があります。
あんこに丸い黄身、なのは同じなのですが、
皮が違います。

こちらは洋菓子の技法が使われてまして、
皮がバター生地でサクサクなんです。
上記の広東式とどっちも美味しいんですが
こんな風に
伝統の料理であっても、
別文化の技法を応用できるっていう点が
とっても興味深いです。
たとえば、
科学的に分析した最新の調理技法を楽しむ
ガストロノミー料理というジャンル
スペインバスク地方の三ツ星「アスルメンディ」の
東京店「エネコ東京」では、
「トリュフたまご」なるメニューがあります。

トリュフと卵は、
フレンチでは定番の超合う伝統の組み合わせ。
ですが、調理法が型破りでして、
こちらの料理は
温めた新鮮な卵黄から注射器で中身を抜いて
トリュフソースを注入して作るんです。
口の中で両方の味が弾ける驚きの料理。
超濃厚な味が楽しめるんです。
この投稿をInstagramで見る
料理に注射器を使う
なんて以前であれば非常識でしたが、
煮たまご
目玉焼き
考えてみれば
いろんな可能性が広がりますよね。
先日紹介したファリッジの料理は、
『温泉玉子の温度帯』を駆使した
新食感のたまご料理ですし、

(参照『海外の新しいたまご料理は、ヒントいっぱい | たまごのソムリエ面白コラム)
ほかにも温泉玉子の技法を利用した
スクランブルエッグ
オムレツ
いろんな面白い可能性があります。
ウチでもいろいろ実験していまして、
時間はかかるけど超おもしろいゆでたまごや
食感のすごい変わった玉子焼きなんかができて
めちゃくちゃ楽しんで
ノウハウが溜まってきています。
ご興味ある方はご一報くださいませ~。
温故知新
昔からある伝統のたまご料理やお菓子でも
ぜひ新たな技法をつかって
繁盛メニューをぜひ
ご研究くださいませ~。
ここまでお読みくださって、
ありがとうございます。