
こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
コロナウイルス禍、大変な状況になっていますね。防疫措置の面では必要な事とはいえ、歓送迎会のシーズンにこの状況なのは、飲食店様にとって本当に大変な状況かと存じます。
先日お取り引き先さんとお話する中で、「こんなことを今やるとイイよね。」という事にきづきましたので、少し書いてみます。
・提供の独自化を狙う!
全国の発症状況を見ていますと、あれだけの混雑でも、通勤電車では感染してないっぽいですよね。やはりしゃべる・食べる・運動などの飛沫が飛びやすい状況が影響しやすいのかなあ、と感じます。
当社の取引先様でも、ビュッフェスタイルからテーブルサーブ方式に一時的に切り替えていらっしゃいますが、『非接触でありながらさらに価値の高まる提供方法』を考案できるチャンスなのかもしれません。
ラーメンチェーン店・一蘭さんの「味集中カウンター」は塾の自習室みたいな一人専用カウンターで食べるわけですが、根強い人気がありながら効率も非常に良い方式なのだとか。
お客様に安心してもらいやすい、ニュー提供方式を試してみる良い時期なのかもしれまません。
・情報発信を楽しむ!
待機や自粛などでヒマな時間が生まれてしまい、ご家庭からオンライン情報のチェックをされている方が増加しています。情報発信の効果は以前よりも高いです。観光地はこのウイルス禍で人が激減していますが、観光地を検索する人は増加しているそうです。「行きたいなぁ…!収まったら・・・」と、調べているんでしょうね。
このタイミングを利用して、時間のかかる動画編集をマスターしてyoutubeへ情報発信している飲食店様もいらっしゃるようです。
・メニュー開発で利益を出す!
普段なかなか時間が取りにくい、研究開発の時間を取ってみるのもいかがでしょうか。
フードコンサルタントの大久保一彦氏は、著書の中で「メインとなるメニューでどれだけ利益を取れるかが、飲食店生き残りのカギだ。」と言っています。
人気メニューのコストダウンや提供の改善って、意外と改まった時間が取りにくいんだそうです。今回を良いタイミングにすることも手じゃないでしょうか。
たとえば、卵のLサイズとMサイズの差はわずか6gですが、10kgケースあたりの入数は15個も変わります。相場価格にもよりますが、もしレシピで6gの差をカバーできれば、1ケース15個の差は年間で大きなコストダウンになるかもしれません。
また、オムレツ専門店さんや洋菓子店さんのように、「まとめて卵を手割りする」ような調理メニューなら、逆に10kgで30個ほど個数が少ないLLサイズの卵なら、作業性が2割くらい効率アップすることもあります。一度作業性を計ってみるのも面白いかもしれません。なかなか普段はこんなこと計測したりしないですよね。
また、当社では和食・洋食・洋菓子・中華で「たまごの比較セット」サンプルを無償でお出しおります。ちょっとどんな卵がウチの料理に合うのか確かめてみよう…!という方にはとてもオススメです^^
今回のウイルス禍が続くなら外食産業さんにとって大変な危機ですが、「どうしようもない」と割り切った上で、今しかできないことを考える、僕たちもぜひそのお手伝いをできればと思います。
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。

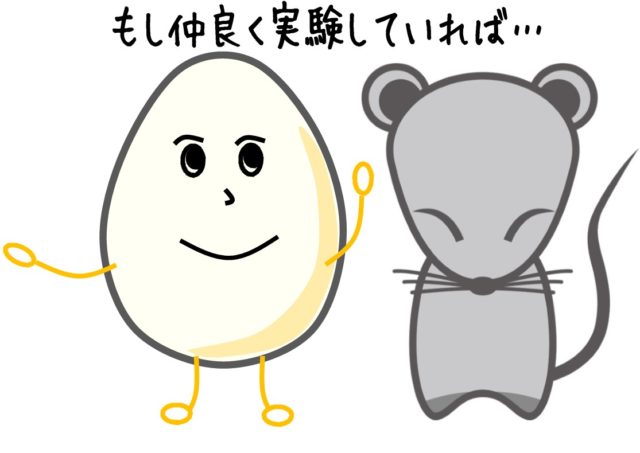

 こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
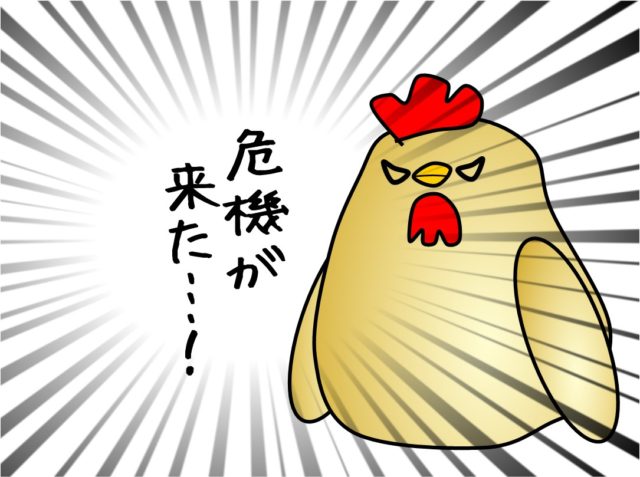 こんにちは!たまごのソムリエ・小林です。
こんにちは!たまごのソムリエ・小林です。
