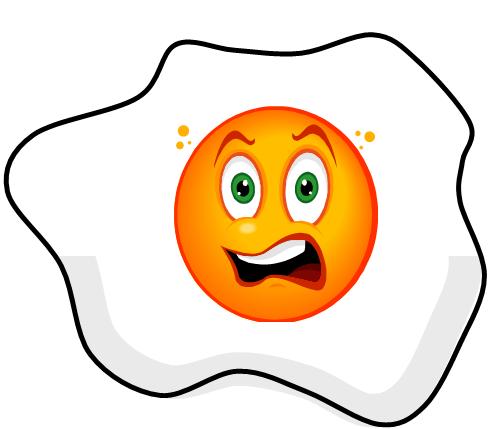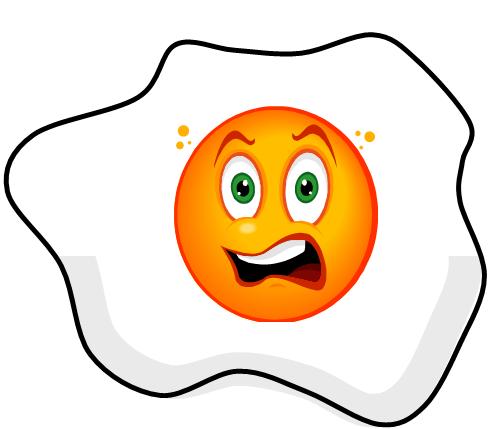
こんにちは!たまごのソムリエ・小林ゴールドエッグのこばやしです。
お盆を前にして、バタバタとしております。(^^;)
こんにちは!たまごのソムリエ・小林ゴールドエッグのこばやしです。
暑い日が続きますねー。息子と半日泳いでいたら、上半身まっ赤っ赤になってしまいました(^^;)
さて、本日はひんやりする話を。
日本でたまごが日常的に食べられるようになったのは、江戸時代から。
それまでは一般的に、卵をたくさん食べるのは「ちょっと恐ろしいコト」だと考えられていた様です。
さて、本日はたまご鶏のちょっと怖い伝説 第二弾です。
————————————–
『沙石集』(1279年・鎌倉時代)
自分の子供にたくさんの卵を採って毎日食べさせている母親がいた。
ある日の夜更け、ふと母親が目を開けると、
子供たちの枕元に女が立っている。
女は
「子供はいとおしいぞ、いとおしい・・」
そう言って泣いている。
そこでハッと目を覚ます。 夢であった。
ところが、程なくして子供たちが次々と死んでしまった。
————————————–
と、いうお話です。
前回ご紹介の「日本霊異記」と同じく、たまごを煮たり焼いたりして食べたら良くない目に合うよ・・・という伝説。 うーん、僕はまさに「子供にたくさんの卵を採って毎日食べさせる親」で、息子もたまご大好きなんですよねェ・・・(ーー;)
日本でたまごが日常的に食べられるようになったのは、江戸時代から。 それまでは一般的に、卵をたくさん食べるのは「ちょっと恐ろしいコト」だと考えられていました。
でも、幕府や都の法律で禁止されていたわけじゃないんですねー。(牛や馬を食べるのは禁止されていました)、 あくまで、仏教の戒律、「殺生をしたらバチがあたる。」という仏教の教えから。
◆影響がすごい!?鎌倉時代ベストセラー本
「日本霊異記」と同じく、この「沙石集」も仏教の教えを広めるために書かれた説話集なんですね。 「沙石集」名前の意味は「沙(すな)から金を、石から玉(宝石)を引き出す」という意味で、

「世俗の他愛ない事柄を使ってホトケの教えを説く」事を目的としています。
内容は非常にバラエティに富んでいまして面白く、後の落語や狂言にもつながっていく大変重要な文学作品でもあります。
ただ・・・・・・、「卵食文化」という観点で見ると、絶大な効果のネガティブキャンペーンになっちゃってるんですねェ・・・。 鶏肉もですが。
なにせこの後、外国文化が受け入れられる1600年代まで数百年間に渡り、宗教的恐怖心から卵を食べる文化が無くなっちゃった訳ですから。(江戸時代まで、卵料理に関する記録は一切存在しないんです)
まぁ、仏教では「殺生がいけない。」という意味で「卵食」を禁じたわけですが、洋の東西を問わず「生命が生まれくる『卵』という存在」を宇宙や高位の存在とする考え方が多数ありますので、殺生うんぬんべつにして「卵は尊い存在だから。」という感覚的な「敬い」の気持ちも理由としてあったのかもしれません。
食に関しては何でも取り入れてしまい、宗教的タブー無く「うまいもん」を追求していくのがザ・日本人である。・・・・・・と思っていましたが、非常に敬虔であった時代もあるんですねェ。
そしてその反動から、江戸時代にはいると卵料理文化が一気に花開き、料理集や卵の煮売り屋台、薬としての卵食文化など、さまざまな形で一般大衆に定着していくことになります。
ここまでお読みくださって、ありがとうございます(^^)
(関連)【納涼】たまご・にわとりのちょっと怖い伝説 その1 – たまごのソムリエ日記