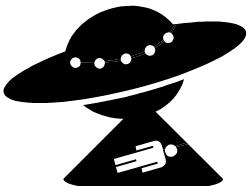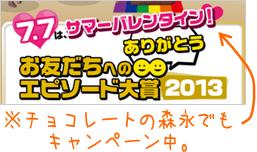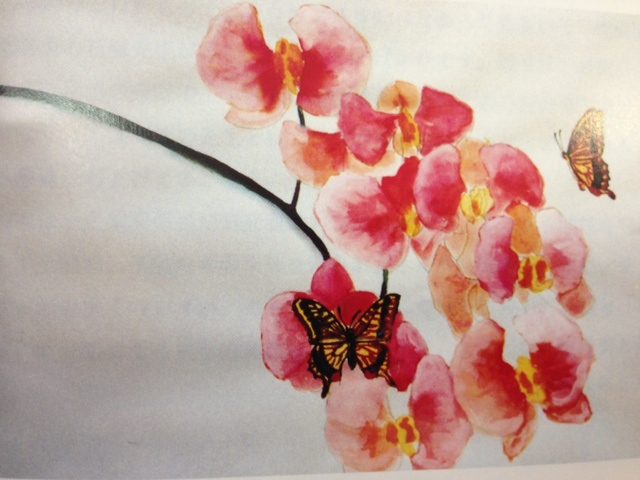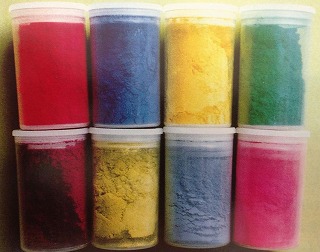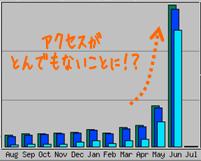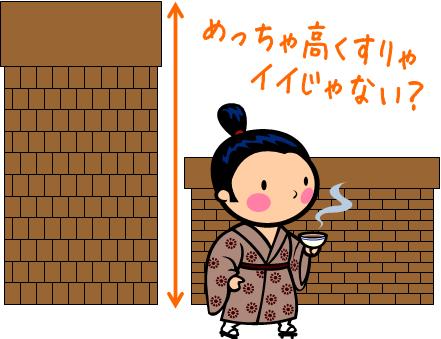こんにちは!たまごのソムリエ・小林ゴールドエッグのこばやしです。
カタパルトで卵を射出し、
数十メートル離れた地点で割らずに卵をキャッチする
・・・という「世界たまご投げ選手権」があるのをご存知でしょうか?

この選手権は、英国のリンカンシャー州Swatonの町で行われている催しです。
なんと!最古の記録では1322年に卵投げが行われており、700年近く前からの歴史ある伝統なんだとか。
かつて、教会の前の川が氾濫した際、渡れずに困った農民達に修道院長が川向こうまで卵を投げて与えたのが、その始まりだそうです。
えー!修道院長、ちょっと乱暴じゃないんでしょうか!?
さて、カタパルトから射出される卵のスピードは時速120マイル(192km)にも達するとの事で、割れないようにキャッチするのは至難の業です。
今年の優勝者は英国のチーム。 57m先でキャッチしたそうですから、メチャクチャすごいですね。(^^;)
他にも、「二人の人間が卵を割らずにどれだけキャッチボールを続けられるか」を競う部門もあったり、とにかく卵キャッチのスペシャリストが集って大盛り上がりの様相です。
日本からもチームで参加しているんですね。 BBCニュースでもインタビューを受けていました(下記リンク)。
個人的には「卵がなんちゅうモッタイナイ(哀)!!」・・・という感覚もあるのですが、ヨーロッパでは古来より「卵をぶつける」という風習がありまして、主に断食の後の謝肉祭(カーニバル)で行われていたそうですので、割れてしまったとしても「神への供物である。」という要素があるのかもしれません。 これもひとつの欧州文化だと理解しています。
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。
卵投げ選手権の詳しい動画は下記をご参照。
BBC News – Competitors gather for egg throwing championships(http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-derbyshire-23118903)