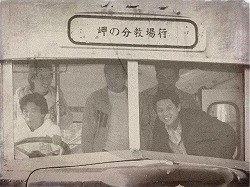こんにちは。こばやしです。
桜の時期まっただ中ですね。 季節が変われば装いも変わる。 春の新作、新しいバッグやアクセサリーが気になってしょうがない方も多いのでは?
さて、世界中にブランドショップを持つティファニー。 このティファニーと「たまご」に深い関係があるのをご存知でしょうか・・・・・・?
◆鮮やかな色、じつは・・・
ティファニーで宝石やアクセサリーを買うと、とってもきれいなブルーの包装紙で包み、同色の商品袋に入れてくれます。
この有名な「ティファニーブルー」、実はある鳥の「卵」と深いつながりがあるんです。
それは「こまどりの卵」。
ウグイスと共に日本三鳴鳥の一つと言われるこの鳥は、きれいな青色の卵を産みます。
ヨーロッパでは古来より「高潔さと真実」を現す色であるこのブルーを、創業者のチャールズ・ルイス・ティファニーは、そのブランドのシンボルカラーとしたんだそうです。
◆青いたまごを食べる
鮮やかな青色のたまご、食べる方としては少々抵抗があるものですが、食用とされていて鮮やかな青色を持つたまごといえば、オーストラリア生まれ「エミュー」のたまごがあります。 ダチョウの親戚さんですね。

元来この色は、草の中では極めて見つけにくい色。 外敵から隠れるのにちょうど良いわけですね。
大きさはコブシ大くらいでかなり大きいです。 カンジンの味は、『味は普通のタマゴよりもリッチでクリーミーな食感、どちらかというとアヒルのたまごに近い食感』だとか。 ダチョウはあるけどエミューのたまごは食べたことが無いので、私も興味深々のたまごです。
実はエミューのたまごには卵アレルギーのアレルゲンとなるたんぱく質が極めて少なく、エミューのたまごはアレルギーのお子さんでも食べられると期待されているようです。
もしかしたら、この「青いたまご」が多くのお子さんの悩みを救ってくれる救世主になるかもしれませんね。
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。